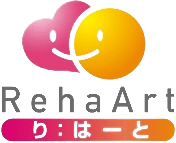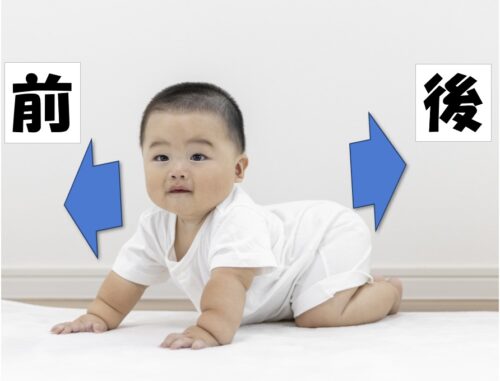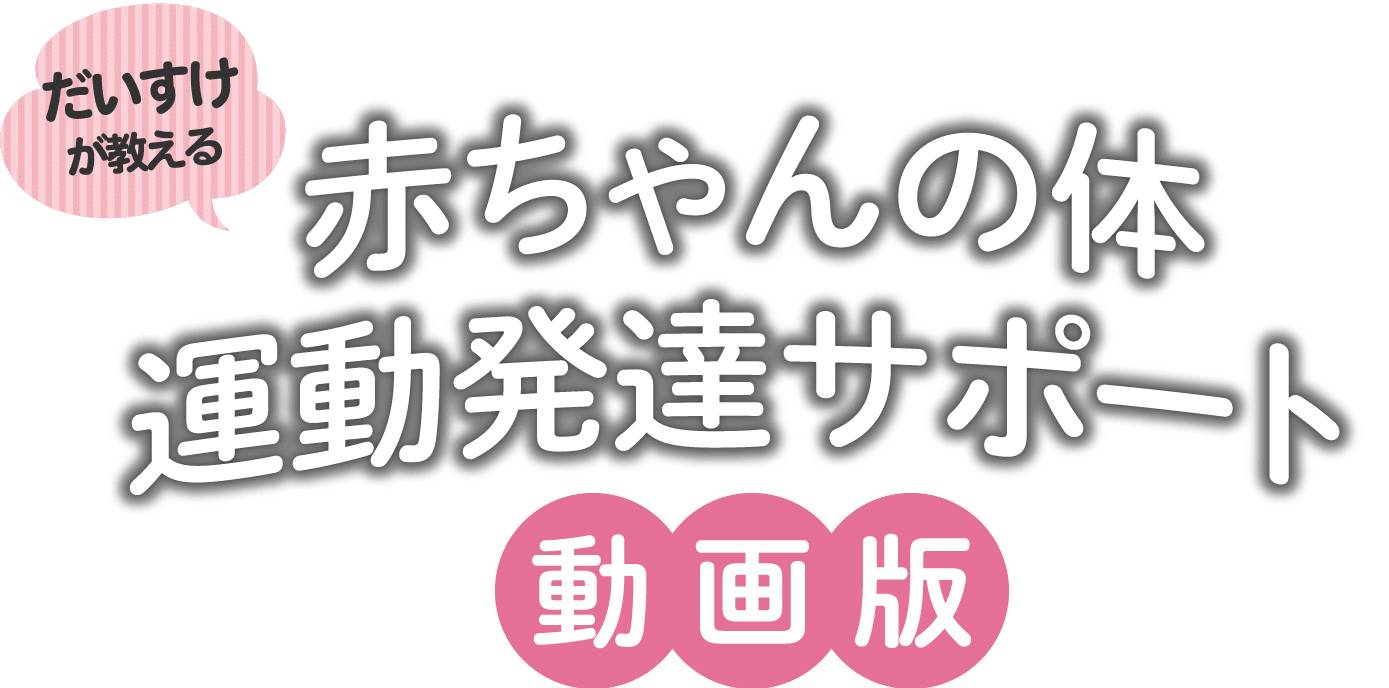2021年8月15日追記
目次
必要な筋緊張は動きのなかで育ちます。だから動きの発達にサポートが必要です。
筋緊張に関する記事の第三弾です(全4回)
赤ちゃん・お子さんがフニャフニャ・・・低緊張なのかどうか?これは正常のわくに収まっているのかがポイントですが・・・前回記事の中にあるとおり正常には幅があるんです。じつは数字で表せるような、検査などは未だありません。
筋緊張の異常はどうやって判断されるのか?
なので、とくに赤ちゃんについては「運動発達の進み具合」と合わせて判断されることが多いと思います。例えば・・・定型発達の時期を半年以上過ぎても、首が座らない・腰が据わらない・歩けない。動作に必要な筋肉が働かない状態で、からだがフニャフニャしていると検診の際などに「低緊張かもしれませんね」といわれるかもしれません。
病院や検診も大事です
ただし生まれた直後から、明らかな「Floppy infant」=フニャフニャ赤ちゃんな場合は染色体異常、その他の先天的な病気の可能性もあります。この場合や、お母さんに不安がある場合一度必ず病院で医師のチェックをお勧めします。(り:はーとでは必ず「定期健診」の受診の有無を確認しますし、病院とのかかわりは重要だと認識しています)
赤ちゃんには「筋緊張を高める」チャンスがたくさん存在します!
赤ちゃんはどんな時に「筋緊張が高まる」体験を育てるのでしょう?本来、まず赤ちゃんの脳・体は自分自身の筋肉があること(存在すること)・動くこと(思い通りになること)この2つを自分自身で気づき、学んでいきます。
そしてそれを土台に「体の緊張を高める体験」を繰り返します。例えば・・・
・お母さんのお腹の中で圧縮されて、押し返す。
・母乳を吸う
・あおむけやうつ伏せで床の上でなることで、重力に押され、そこから支える。
・丸まり抱っこで圧縮されて、押し返す。
・頭を持ち上げる。
・ウンチをする
・ずりばいをする。
・お腹を床から持ち上げる。
・四つ這いをする。
・つかまり立ちをする。
・自らお母さんにしがみつく。
・スクワット(一人で歩く前後の時期)をする。
・しっかりと安定した抱っこやおんぶも、「体の緊張を高める経験」になります。
代表的なものだけでもこれだけあり、さらに実際にはあらゆる場面に経験のチャンスが隠されています。だからお子さんがこれらの経験をしやすいように体や環境を整えてあげることが必要です。上に書いたような「緊張を高める体験」は細切れの動きではなく動きの発達のプロセス全体の中で起こります。
り:はーとでの体の柔らかい・硬い赤ちゃんとのレッスン
り:はーとでは特に「フェルデンクライス・メソッド」と「シェルハブ・メソッド」の動きやタッチを使い、遊びの中で赤ちゃんが「筋緊張を高める」経験を蓄積できるようにサポートしています。
シェルハブメソッドの創始者「ハバ・シェルハブ博士」は赤ちゃんの頭の中に「体の地図」ができていることが大切だと述べています。このメソッドの、ポンポン(tapping)・ムギュウ(squeezing)といったタッチの手法も筋緊張を整え、筋肉が働く土台となる身体の認識を高めることを助けます。※たなかは現在この「シェルハブ・メソッド」のトレーニングに参加しています。
たくさんのかかわり方があると思いますが、「筋緊張を高める」チャンスを生かし、赤ちゃんがたくさんの経験を積み重ねていけるように、ぜひ遊びながら関わってあげてくださいね。
次回の記事では、具体的にできるタッチの方法について紹介します。
このシリーズ記事の最後は「体の硬い赤ちゃんにできること(4/4)」です。
子ども向けレッスンの詳細はこちら