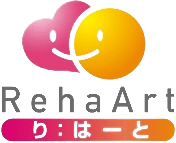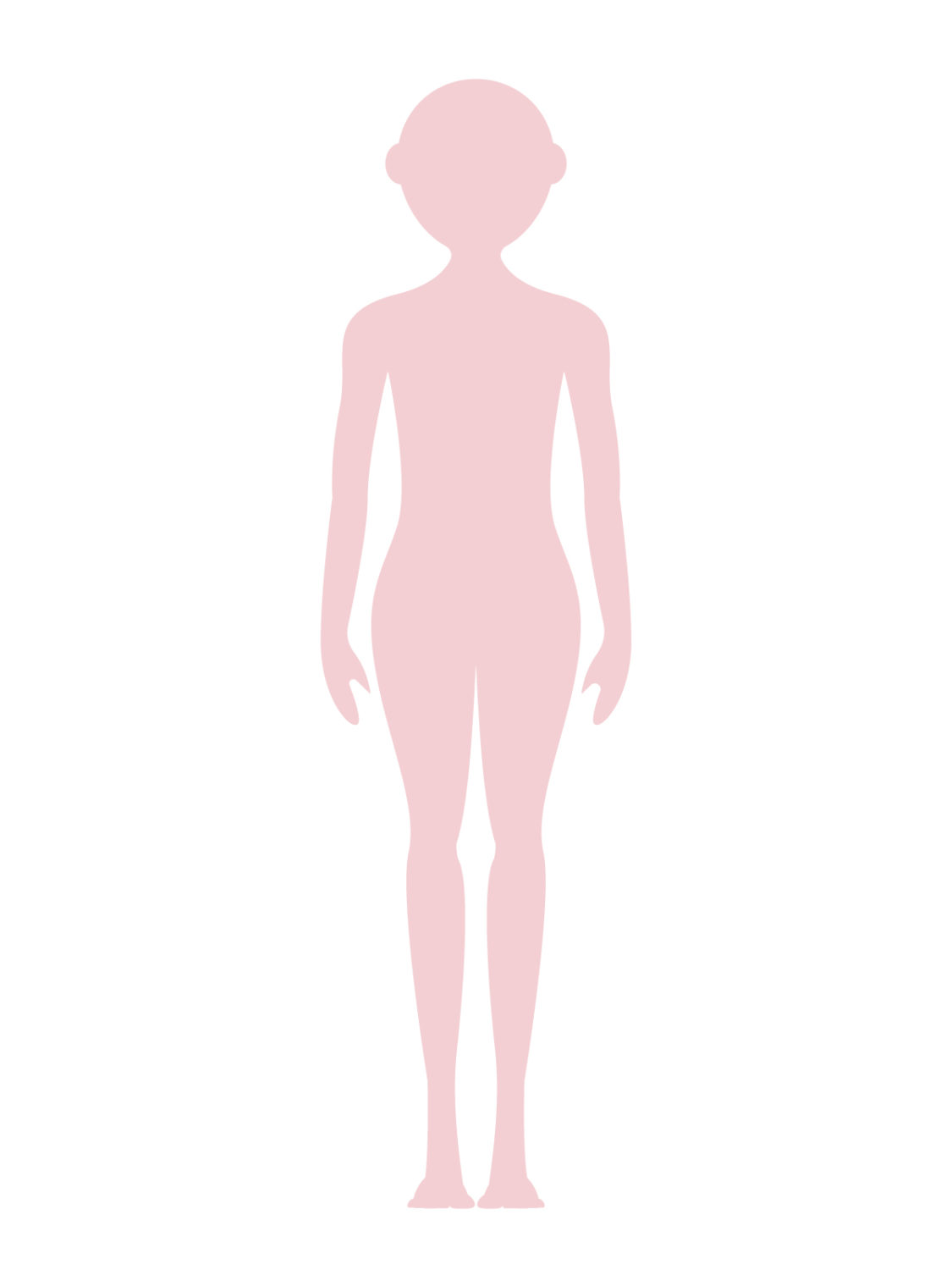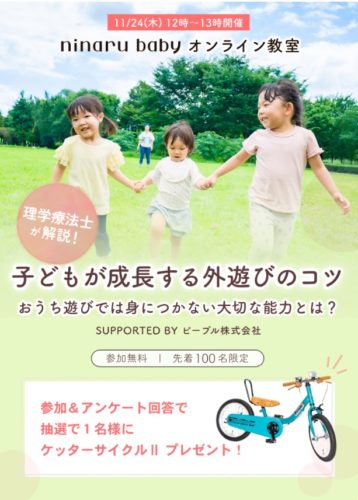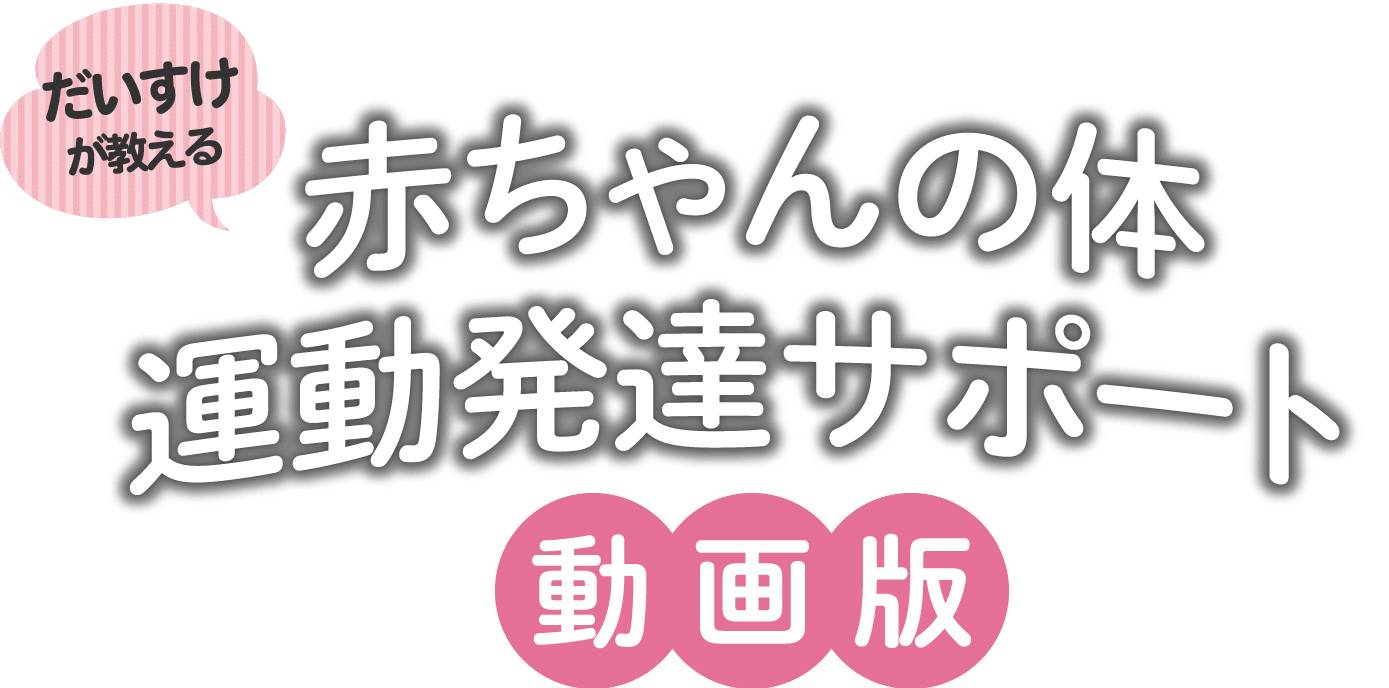目次
■姿勢が悪い・・・ご両親にとっての悩みの種のひとつ。
この相談は当スタジオの子ども向けレッスンをお問い合わせの際に、とくに多いものです。それだけご両親にとって悩みのたねです。
座り姿勢・立ち姿勢、運動の場面で目立ちます。
つい「ちゃんとしなさい」「姿勢を良くしなさい」と言ってしまいたくなるのですが・・・じつはお子さんにとってこの言葉が一番難しいのです。
なぜご両親の思いは伝わらないのか?お子さんはきっと、何とか姿勢を治そうとしているはずです。なのに思うようにいきません。そればいったいなぜだと思いますか?
■姿勢を簡単には直せない3つの理由
①体がフニャフニャと柔らかい。
これらは「筋緊張が低い・関節が柔らかい」お子さんのことです。
そもそも私たちの体を作る筋肉の張り具合(筋緊張)や関節の遊びには、大きな個人差があります。そしてみんな「健康」の範囲内です。
⇒「筋緊張」について紹介しているこちらのブログもご覧ください。
体を支える重要な構造は「骨格」≒骨が積み木のように積みあがって出来た形です。体の重さは支柱である骨格によって支えられています。筋肉や関節はこの骨の積み木が崩れないように引っ張り合って支えています。
フニャフニャしているようにお母さまが感じるお子さんは、この特徴を持つがために身体を支えるのにかなり上手に体を使えないとならず、これは大人にでも大変なことです。
それと同時に支持や高めた緊張を「維持すること」も苦手なため、ちょっと頑張って見せてもすぐに、寄りかかったりひどいと寝っ転がってしまいます。
②体の動きを知らない
身体は実際に動いて、その経験をもとにたくさんの「バリエーション」を身につけます。ところがすべての人間は、例えば赤ちゃんが立ちあがるまでの成長のなかでも、ひとりひとりみんな違うプロセスの中にいます。
だから、私たちすべての人間には「経験できなかった動き」があるはずなのです。
とくにハイハイや四つ這いの未経験や経験不足(うまくなるまでやり切らなかった・・・これも結構います)のあったお子さんには、このときの体幹や股関節の動きをうまく使えないということが起こりやすいです。
⇒ハイハイで経験される機能について紹介しているこちらの記事もご覧ください。
③自身の姿勢をイメージできない。
私たちの脳は「ボディイメージ」といって、自分の体の姿勢や大きさ・形・関節などをまとめた「地図」のようなものを持っています。シェルハブ・メソッドでは「ボディマップ」とも呼びます。
本来0才児の頃から、見て動いて触ってなめて・・・とたくさんの感覚体験の中で培われるのですが、これの力が育っていないことがあります。
自身の姿勢をイメージできないということは、お母さんがいくら見本を見せても「分からない」ということです。
自身の体のイメージは、空間の中の自身の位置や方向とも関連しています。
何かによくぶつかったり、またぐことやテーブルをくぐったりすることが苦手の子にも、「空間の中の自分」をとらえるのが困難なことがあります。
■体幹を使えるようになることは筋力強化とイコールか?
世の中にはたくさんの「筋トレ」のメニューがあります。体幹というと・・・スポーツ選手のシックスパックのようなムキムキの体幹を想像する人も多いことでしょう。
あのようながっちりとした体幹によって得られるのは「固定」「空間における安定」で、スポーツ選手はさまざまな競技特性のためにあのような体幹を必要としています。
しかし、子どもたちはどうでしょう・・・
子どもの筋トレはあまりないですよね?
まず第一に身体は筋肉ではなく骨格で支えられています。そして、骨格と関節が動きを作ります。筋肉は動きのエンジンですが、動きの経験のうえでは助けにも邪魔にもなります。
だから、子どもの体幹が弱いなご両親が感じたときに起こっていることの多くは・・・力が足りないのではなく、体幹を「動かせない」もしくは「うまく使えていない」ということです。
■子どもにも肩こりや腰痛が現れる!?
また、すでに小学生や中学生から大人と同様に、腰・背中・肩に緊張や痛みを感じるお子さんさえいます。
これらのトラブルは、体をうまく動かせないことや、本来不必要な固定によって生じます。
日常の生活や勉強・部活などの運動に影響してしまう前に、サポートが必要です。
そんなときには、大人のように「揉んで治す」のでしょうか?
現れるトラブルは大人と同じですが、子どもの体は大人と違います。骨格の構造も筋も、神経系もまだまだ未成熟です。
だから一時しのぎのマッサージだけよりも・・・将来のために、その心身の成長を理解しつつ自由に動ける体をめざしていくことをり:はーとではお勧めします。
■体幹と姿勢と飲み込み・歯並びへの影響
食べるときの姿勢もご両親が気になる場面の一つだと思います。
実は単に見たの問題だけでないのです。座り方は頭や首、もっと言えば口や舌、噛んで飲むことにつかう筋肉・関節の動きに影響を及ぼします。
また口の中にある大きな筋肉である「舌」も姿勢の影響を強く受けており、その位置や動きは歯並びにも大きな影響を与えていることが、小児歯科の先生方より示されるようになってきました。
ぽかんと開いた口、舌の動きの苦手、飲み込み苦手、すすりの苦手、歯並びのトラブル、咬合の不全・・・これらの悩みにも「姿勢」とそれを支える体幹の動きは考える必要のある重要な項目の一つとなっています。
子どものとくに座り姿勢を考えることは、美観・体の健康についで食の問題にもかかわってきます。
■机上の活動・勉強に集中することと座るということ
良いと思われる・もしくは見える姿勢は「安定」しています。例えば、えんぴつやはさみ、コンパスなどの道具をスムーズに使おうとしたときに、安定した姿勢は欠かせません。
お子さんがえんぴつで文字を書いているときなどに、背中を丸めたり、肩がすくんでいたら・・・手先(末梢)を細かく使うための、体幹(中枢)の安定が不足しているということです。この場合には指先に安定を作るために、肩・腕・指先に力が入ります、「力を入れないで!」とどんなに伝えてもお子さんには力を抜けません。
また、目の機能も安定した体幹と頭の関係性が必要です。目も手足と同じように筋肉で動きており、その筋肉は頭の骨についています。土台が安定しないと、目を細かく動かすこと、頭の動きと分化することが難しくなります。
しっかりと木の幹に、柔らかくしなる枝葉がつくことをイメージしやすいと思います。つまり必要なのは、手先の動きや目の動きをスムーズにするための「体幹(中枢)の安定⇔手先・頭(末梢)の動き」という関係性です。ここでもしっかりと支えて動きる体幹は大事になってくるのです。
そして、安定している身体は同時に勉強に集中することの助けにもなります。
■サッカーや野球、ゴルフなどのスポーツに取り組む
今までの話は、「椅子に座って」のものが多かったのですが、ここではお子さんの取り組むスポーツとの関連です。
もっとうまくなりたい、強くなりたいと努力しているときに、もしもご両親の目から見ていて背中が丸まっているなど、「うちの子姿勢が悪いな」と感じることがあったとしたら・・・より上手になるためのヒントは「体の使い方」にあるかもしれません。
ここでの姿勢の悪さは、座位で感じることも、立ち姿勢で気がつくこともあるでしょう。
より高度なバランス、複雑な動きのスキル、それだけでなくもっと速く走る、高く飛ぶ、方向転換などそんなシンプルな活動にも体幹の動きは影響しています。
また、ケガの予防、起きてしまった故障と再発予防の観点からも「体の使い方」を養いことが必要です。
■「動き」そして「姿勢」を変えるり:はーとのレッスン
姿勢に悪さ、体幹の弱さに対して、り:はーとのレッスンがどのようにアプローチするのか?
ここまでの話から「筋トレ」ではなく「動き」の学習が必要だということはすでに、お分かり頂けたことと思います。
それでは、姿勢はどうやって変えるの?と思われるでしょう。そもそも姿勢は「動き」のある瞬間一部を切り取ったものです。なので、レッスンでは動きの中でたくさんの「姿勢」を経験することとなります。
逆に言えば「動き」を考えずに「姿勢」を変えることはできないのです。
座った時の姿勢は赤ちゃんのときから培われ始め、それは椅子にすわることよりも「床で座る」ことによってです。
り:はーとの中核となる「フェルデンクライス・メソッド」は運動学習を効果的に行うための、新しいアイデアです。また赤ちゃんのころに経験する寝返りやハイハイといった発達上の体幹の動きを「シェルハブ・メソッド」を応用してたくさん追体験していきます。
これらを用いて視覚・触覚・前庭感覚・固有感覚といった感覚と運動発達動きを結びつけるように学ぶことで、お子さんの
①筋緊張を高め・維持する活動
②動きの経験
③ボディイメージの獲得・拡大を目指します。
から、体幹の機能向上と姿勢の改善を目指します。
■できるようになりたいと思う「子どもの気持ち」によりそう
さらに子どもが学び・成長するためには子ども自身が主体的であることが欠かせません。
レッスンを行なう際に行なう遊びや動きは、お子さんとよく話してから決めていきます。
その子自身が「興味を持っていること」や「出来るようになりたいこと」を中心において、教師が毎回その日のレッスン内容をアレンジしていきます。
このことで、多くのお子さんが「またスタジオに来たい」と感じるになります。
ぜひり:はーとのレッスンをお受け頂き・・・
お子さんが笑顔で「新しいことに挑戦している姿」をご両親に驚いて頂けることを楽しみにしております。
子ども向けレッスンの詳細はこちらおすすめ記事はこちら