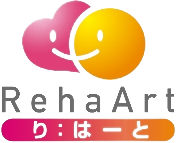それは「主導権はお子さんにある」ことの現れです。
お子さんへのレッスンをしていて・・・。
「もっと痛くても動かす」イメージでしたとおっしゃるお母さんがいました。
そのような話しを伺うのは、実は今回で「2回目」です。
共通点は・・・お二人とも「療育」の経験があるということ。
自身も理学療法士として療育の現場にもかかわっているので・・・。
ときにセラピストの事情(評価やレポート)で痛くても動かさないといけなかったり
まれには・・・セラピストのやりたいこと(治療)を優先するあまり
泣き叫んでいても動かすことがある(そういうセラピストもいる)と聞きます。
り:はーとで「フェルデンクライス」をベースにした子ども向けをレッスンをおこなっています。
各種療育技術や民間の体操などとの大きな違いは主体が「お子さん自身」であるということです。
つまり、決めるのはいつもお子さん側だということ。
教師側がその日何をするか決めないで関わり始めるのも、そのせいです。
つねにお子さんの興味の中にいて、それを発展していくために
直接のタッチだけではなく、道具、環境、方法など
さまざまなレベルで「いつの間にか」関わっています。
本当の学びこそ、お子さんたちの脳を育てるとたなかはそう信じています。
その結果、ほとんどすべてのお子さんが
「楽しかった」「また来たい」という感想というになります(笑)
それは教師にとって最高の褒め言葉で・・・その繰り返しの中にお子さんたちの本当の学びと変化がある。
ここまで読まれて、り;はーとのレッスンはどんな感じなんだろうと思われた方は
ぜひこちらのフォームより詳細についてお問合せください。